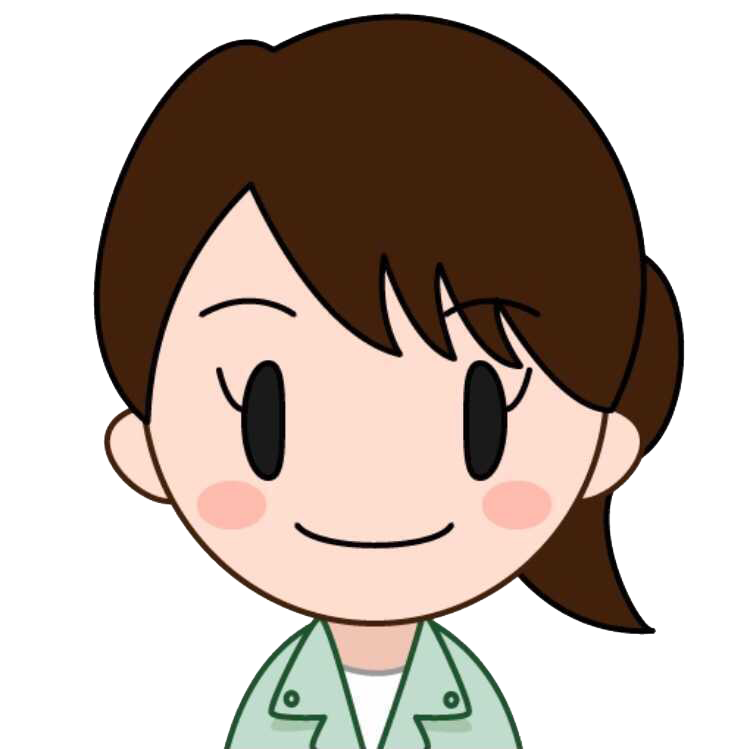| タイトル |
生物や社会の形態パターンを再現する新モデルの創出 |
| 担当機関 |
(国研) 水産研究・教育機構 水産大学校 |
| 研究期間 |
2019~2022 |
| 研究担当者 |
石田武志
|
| 発行年度 |
2020 |
| 要約 |
生物の形態形成を説明する理論の一つにチューリングモデルがある。これは拡散係数が違う活性因子と抑制因子の2種類の物質の濃度差により、非線形作用により自己組織的にパターン(チューリングパターン)が形成されるものである。本研究は、1種類の物質(モルフォゲン)の経時変化と隣接相互作用だけでもチューリングパターンを形成することができることをコンピュータモデルにより示したものである。
|
| 背景・ねらい |
局所的な相互作用のみから大域的な構造が生まれる自己組織化現象は、生物などの自然界や人間社会でも多くみられる。本現象を引き起こす条件を明確にできれば、その制御も可能となる。代表的な自己組織化モデルとしてチューリングモデルがあるが、実生物でこのモデルの機序に相当する2種類の物質が特定され、濃度差を利用した形態形成の証拠が確立した段階には至っていない。本研究では、2種類の物質が必要だと考えられていた概念に対し、1種類だけでもチューリングパターンを形成することが可能であるか試みた。
|
| 成果の内容・特徴 |
計算ではセルオートマトンモデルという、空間上に分布した各セルの状態が隣接するセルの状態によって時間ステップごとに変化していく、空間と時間を離散化したモデルを利用した。具体的には、2つの状態(赤、青)のセルを考え、赤いセルはモルフォゲンを産出するとする(図1)。モルフォゲンは隣接セル(の表面)に拡散し、そこで修飾され状態が変化(1段階から2段階)する。そのモルフォゲンは一部を残して更に隣接セルに移動し、更に修飾される(2段階から3段階)ことを繰り返し、X段階まで修飾されていく。この各セルに残る1~(X/2-1)段階とX/2~X段階のモルフォゲンの比率wにより、次のセルの状態(赤か青か)を決定する。そして、隣接セルの状態を決定するパラメータwを変化させると、チューリングパターンモデル同様、斑点模様や縞模様が出現することを明らかにした(計算結果の一例を図2に示す)。これにより、当該モデルにおいて1種類の物質の経時変化を考慮することで2物質の拡散濃度差に相当する情報を表せたと考えられる。
|
| 成果の活用面・留意点 |
今回のアルゴリズムのモルフォゲンの挙動は、細胞内タンパク質のプロテオリシス(ペプチド鎖の切断)のメカニズムで容易に実現できる可能性がある。このモルフォゲンが隣接セルに移るたびに変質する過程はプロテオリシスに相当すると考えられ、実生物における形態形成のメカニズムと対応が容易になり、今後、本モデルの観点から生体内でのモルフォゲンを探すことで、生物の形態形成機能解明の一助になると考えられる。また、生態系の種分布パターンや様々な社会現象の説明にも応用できる可能性がある。
|
| 研究内容 |
http://fra-seika.fra.affrc.go.jp/~dbmngr/cgi-bin/search/search_detail.cgi?RESULT_ID=10062&YEAR=2020
|
| カテゴリ |
トマト
|