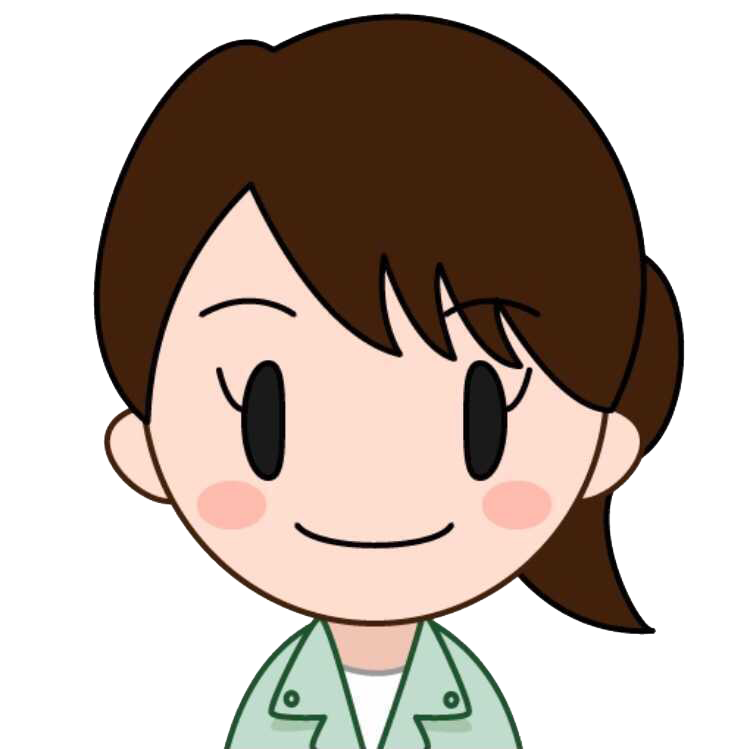樹木の種子生産戦略 -かしこい子孫の残し方-
| タイトル | 樹木の種子生産戦略 -かしこい子孫の残し方- |
|---|---|
| 担当機関 | (独)森林総合研究所 |
| 研究期間 | |
| 研究担当者 |
柴田 銃江 新山 馨 田中 浩 |
| 発行年度 | 2002 |
| 要約 | 多くの森林樹木には、マスティングとよばれる種子の「成り年」現象がある。温帯落葉広葉樹林での地道な長期観測結果から、マスティングには種子食者から上手く逃れたり、受粉効率を上げるなど、樹木の種子生産戦略上の特別な利点があることがわかった。 |
| 背景・ねらい | 広葉樹林の保全と管理には、樹木の繁殖に関わる生態的特性をいかし効果的に利用することが必要である。樹木の種子生産には大きな年変動がある。例えばブナの場合、豊作年には地面に敷き詰められるほどの実が落下するが、凶作年にはまったく実が見られない。このような「成り年」現象はマスティングと呼ばれ、世界中の様々な森林で報告されている。マスティングがおきる理由は、ある年に昆虫やネズミが食べ切れないほど種子を実らせて、多くの種子を生き延びさせたり(飽食仮説)、まとまって開花することで、受粉の効率を上げ、健全な種子を増やす(受粉効率仮説)など、何年かに一度、まとまった資源を花と種子に投資することで、多くの子孫を残すという利点があると言われている。 しかし、実際の森林で、マスティングの利点に関する仮説を定量的なデータをもとに検討した例はきわめて少ない。そこで、茨城県北部の落葉広葉樹林にある長期生態研究調査地(「小川試験地」)で、主要構成種の種子生産数を長期間測定し、そのデータをもとにマスティング現象の実態とその利点を明らかにした。 |
| 成果の内容・特徴 | 小川試験地では、多数の種子トラップ(図1)を使い、当所実験林室の協力のもと14年以上、種子生産数を継続調査している。このうち種子の同定と測定が済んだ16樹種の9年間の種子生産数の年変動を解析した。その結果、各樹種の豊凶の変動幅は樹種により大きく異なるが、豊作、凶作年が一致する樹種の多いことがわかった(図2)。例えばイヌブナやハリギリは豊作と凶作年の差が著しいが、コナラやミズナラは豊凶の変動幅が小さかった。豊作と凶作年が一致したイヌシデ、アカシデ、クマシデ、サワシバは、同じクマシデ属の近縁な樹種である。同様にカエデ属のイタヤカエデとオオモミジも豊凶のパターンがよく似ていた。さらに、ブナ、アサダ、イタヤカエデの3種は近縁ではないが、部分的によく似た豊凶の年変動パターンを示していた。 このような森林群集全体でおこる豊凶の年変動パターンの一致は、どのようなしくみでおこり、樹木にとってどんな利点があるのだろうか?データを解析した結果、近縁な樹種がより同調した種子生産の年変動パターンを示すこと、近縁の樹種が同調することで豊作の年ほど、それぞれの樹種の種子の虫害率も低くなることがわかった。このことから、異なる樹種で種子生産数の豊凶が同調すると、豊作年には互いに共通の種子食者を飽食させたり、凶作年には飢えさせ、種子食者を減少させる効果があると推測された。 また、この森林を構成する多くの風媒樹種は、開花量が多い年ほど秋にできる健全な種子数も多く、しいな率が低くなった。このことから豊作年ほど受粉効率が上がり、健全な種子をつくることができる利点があると考えられた。この利点は、各樹種ごとの問題なので、森林群集全体で豊凶が一致する理由とは直接には結びつかない。しかし、それぞれの樹種内の個体が同調して開花する条件(例えば花芽形成を促進する前年の高温や乾燥)が限られる場合、異なった樹種でも同じ気象条件を開花条件として用いるので、結果的に近縁でない樹種でも同調した豊凶がおこる可能性はある。 このような長期観測を今後も継続し、各樹種の種子生産データを充実させる一方、花芽形成に関わる様々な気象要因、種子食の昆虫や小型哺乳類の生息数、受粉から受精までの種子の生存過程などに注目したきめ細かい観察を積み重ねることで、樹木の生存戦略やそれに関わる生物間相互作用の役割が、より明確になると期待される。生物間相互作用の多様性を含む森林の生物多様性全体が保全されて初めて、豊かな広葉樹林の保全と管理が可能になる。 |
| 図表1 |  |
| 図表2 |  |
| 図表3 |  |
| 図表4 |  |
| カテゴリ | かえで 乾燥 受粉 繁殖性改善 |