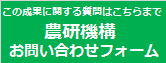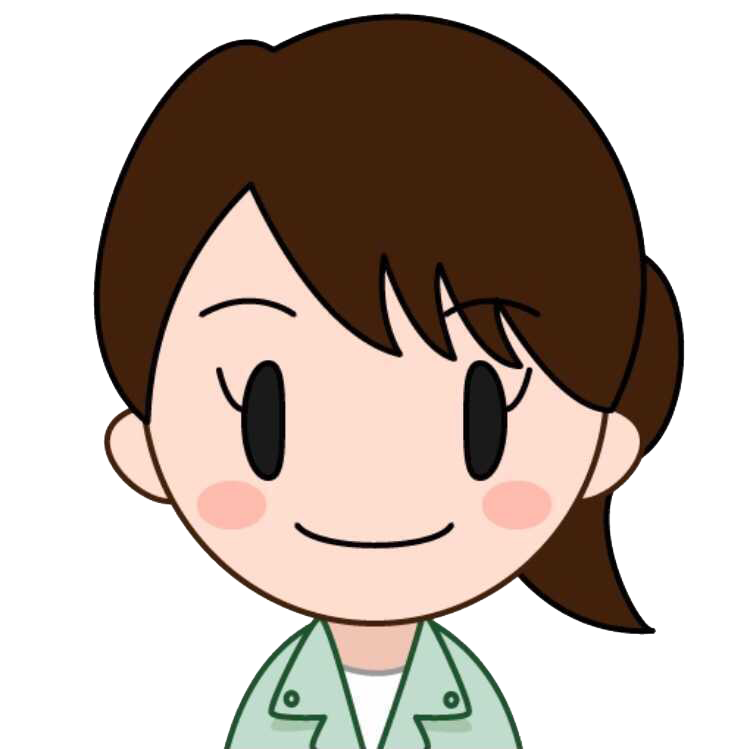| タイトル |
ウシラクトフェリンは哺乳子牛の急性相反応を制御する |
| 担当機関 |
(独)農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所 |
| 研究期間 |
2006~2008 |
| 研究担当者 |
櫛引史郎
伊藤文彰
押部明徳(東北農研)
三谷朋弘(北大)
守谷直子
小松篤司(東北農研)
新宮博行
嶝野英子(東北農研)
|
| 発行年度 |
2008 |
| 要約 |
ウシラクトフェリンの哺乳子牛への経口投与は、エンドトキシンによる免疫、代謝、内分泌機能の変動を緩和する。この制御作用はウシラクトフェリンがエンドトキシンによる腫瘍壊死因子等の炎症性サイトカインの過剰な産生を抑制するためである。
|
| キーワード |
ウシラクトフェリン、急性相反応、哺乳子牛
|
| 背景・ねらい |
哺乳期の子牛は免疫機構が移行免疫から自立した免疫への移行期であるため、下痢や肺炎などの感染症にかかりやすい。加えてこの時期はサイトカインの産生能が不安定なため、本来であれば生体防御である急性相反応(APR)が過剰となって予後不良やへい死に至ることが多い。
そこで哺乳子牛の損耗率低下を目指すため、ウシラクトフェリン(LF)の抗炎症作用を利用して、哺乳子牛の過剰な急性相反応を緩和する免疫調節効果を明らかにする。
|
| 成果の内容・特徴 |
- ホルスタイン種雄子牛20頭をLF区(10頭)と対照区(10頭)に分けて、生後3日齢からLF区の子牛にLFを朝夕の牛乳に混和して10日間給与する(3g/日)。
- LF給与期間終了の翌日にエンドトキシンとして大腸菌由来リポポリサッカライド(LPS;055:B5、50 ng/kg BW)を頚静脈から投与して、96時間後まで経時的に採血して血漿を分離する。LPS投与後の哺乳用牛乳にはLFは混和しない。
- 炎症性サイトカインである腫瘍壊死因子(TNF)の血漿中濃度はLPS投与2時間目に一過性のピークを示し、LF区のピーク値は対照区より約40%低減する(図1)。また、インターロイキン(IL)-1の血漿濃度もLF区では上昇が抑制される(文献2)。
- 炎症マーカーとしてAPRレベルの指標となる血漿ハプトグロビン濃度は、LPS投与後両区で上昇するが、LF区の変化は対照区に比べて小さくなる(図2)ことから、LPSによるIL-6産生がLF区で低くなることが示唆される。
- アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)濃度はLPS投与によって増加するが、24時間以降はLF区が対照区よりも低く推移する(図3左)。また、血漿中インスリン様成長因子(IGF-1)濃度はLPS投与にともなって減少するが、LF区の変化は対照区に比べて小さい(図3右)。
|
| 成果の活用面・留意点 |
- LFの哺乳子牛への経口投与がLPS誘導急性相反応を制御することを示した初めての知見である
- LFの抗炎症作用およびサイトカイン調節作用を解明する上で有用な情報である。
- LFの給与量を1g/日に下げても同様の効果は認められるが、感染試験でのLFの有効性は未検討である。
|
| 図表1 |
 |
| 図表2 |
 |
| 図表3 |
 |
| カテゴリ |
|